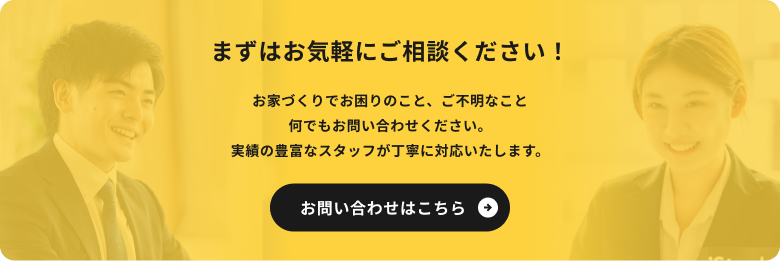- 不動産売却
- #家づくりコラム
査定の流れについて(原価法)

今回のコラムでは、不動産の査定方法である『原価法』について解説します。
『原価法』とは、主に建物部分の査定で用いられる不動産の査定方法の一つで、今ある建物を壊して同じものを新しく建てた場合の費用(再調達価格)を算出し、そこから経年劣化による減価(減価修正額)を差し引いて現在の価値を求める方法です。
一戸建て住宅の査定では、土地と建物の価値を別々に算出して評価を行います。
なぜなら、土地は経年劣化などの影響を受けないものの、建物は建築直後の価値が最も高くなるため、経年劣化などの影響を受けて価値が減少してゆくからです。
原価法の計算は、
「再調達価格(1㎡あたりの再調達単価×延床面積)×減価率(残存年数 ÷ 耐用年数)」で行います。
ここからは、原価法で査定を行う場合の詳しい手順をご説明いたします。
1. 再調達価格の算出
現在同じ建物を新築した場合に必要となる建設費(再調達原価)を計算します。
1㎡あたりの再調達単価を調べ、延床面積を掛けて全体の再調達価格を算出します。
建設費は、国税庁が公表する「建物の標準的な建築価額表」などを参考にします。
2. 減価修正額の算出
建物の築年数や状態に応じて、経年劣化による減価額を計算します。
減価修正額は、再調達価格に減価率をかけて計算します。
より詳細な査定をする場合、減価修正は築年数だけでなく、建物の状態や地域、構造など、様々な要因を考慮する必要があります。
3. 査定額の算出
再調達価格から減価修正額を差し引いて、建物の査定額を算出します。
いかがでしたでしょうか?
冒頭でご紹介したとおり、『原価法』はあくまで査定の一つの方法であり、『取引事例比較法』や『収益還元法』と組み合わせることで、より正確な査定結果が得られます。
『取引事例比較法』や『収益還元法』については今後のコラムにてご紹介予定ですので、そちらも参考にしてみてください。
家づくりカウンターでは、経験豊富なスタッフがお客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
もちろんご売却だけでなく、お住み替え用の物件(購入・賃貸)のご紹介も可能ですので、まずはお気軽にご相談くださいませ!
執筆者 家づくりカウンターゆめが丘ソラトス店 香川尚子